PTから病院の売店で本を買って読むように言われた。(脳卒中のリハビリティーション)という本である。テレビも無い大部屋だったから穴があくほど読んだ。M病院では止血の点滴以外、これといった積極的な治療はなかった。院長が手術の必要はないという。出血の場所は脳の奥深くにある視床下部というところだと説明を受けたが、そこがどのうような機能を司るのか知る由もなかった。
<故郷へ>
1月下旬。良枝さんに車椅子を押されてリハビリ室に入った。与えられた訓練メニューを一通りこなすと、私は、ぼんやりと窓から外の景色を眺めていた。
「山下さん、ここは那覇というところですよ。僕は若い頃、研修生のときですが、福岡の春日にいました。知っていますか?」
リハビリの先生が背後から話しかけてきた。福岡という地名を聞いたら母の顔が思い出された。母の顔が脳裏に浮かぶと声までも聞こえてきそうで、涙がボロボロ出てきた。病気になってからちょっとしたことで、目がウルウルになってしまう。
「先生、向こうに帰りたいのですが」
いつになったら帰れるか。気がかりだったので思い切って尋ねた。
「そうですね。その方が良いでしょうね。後で院長と相談してみましょう」
「山下さん、ヤマトに帰りたいよね。その方がいいよ」
良枝さんは微笑ながら優しく言った。彼女の口から発せられた「ヤマト」という言葉から琉球が大和民族に支配されていたことが連想された。戦国期に薩摩の島津氏の支配は人頭税を課したということを本で読んだ記憶があった。
転院の許可はすぐに下りた。準備は嫌な奴だが中村工事部長に委ねるしかなかった。さっそくその晩、実家に電話を入れた。
「馬場病院に入院予約ばしたけん。飛行機の便がわかったなら留次郎ば迎えにやるたい。そいけん安心しとかんね」
電話に出た母からこんな答えが返ってきてほっとした。福岡に帰る日、良枝さんは、僕と中村工事部長を自家用の白いセダンに乗せると那覇空港まで送ってくれた。彼女は、空港のロビーに着くと、
「飛行機の中で食べてね」
と言ってラップに包んだサンドイッチと茹で卵を渡してくれた。優しい良枝さんのいつまでも手を振る姿が忘れられない。

那覇空港を飛び立ったのは2月の3日である。介助者として中村工事部長が付き添った。JALの係員が車椅子をダグラスDC10の機内まで導いてくれた。中村さんが尿瓶を持って隣の座席に座った。幸いなことに尿意はおきなかくてほっとした。福岡空港に着いたのは午後2時過ぎだった。
福岡空港の到着ゲートを出ると、留次郎と嫁の美知子さんが自家用車で出迎えにきていた。飛行機から出ると、JALの係員にたばこのハイライトを買ってきてくれるように頼んだ。久しぶりのタバコに酔いしれていると、
「兄ちゃん、タバコはいかんばい。お医者さんから、そげん言われとるけん」
弟は兄の手から強引にタバコを奪った。私は、車に乗ってからもまだタバコに未練があった。
「おい、留次郎、一本だけ吸わせてくれんか、よかろうもん」
「いんにゃあ、いかんいかん」
「あなた、お兄さんがあんなに言うてやけん、1本出してやらんね」
美知子さんが見かねて言った。
「おまいまでなんば言うか、いかんて言うたら絶対いかん」
僕たちが乗った車は国道3号線を南下した。筑後川を渡り、久留米の市街地を抜けるとやがて車は故郷の馬場脳神経外科病院意到着した。両親が心配げな顔で待っていた。母の顔を見たとたん目が潤んだ。案内された大部屋で一夜を明かすと、翌朝の9時から点滴、それからリハビリ室での訓練がが始まった。
<頭蓋骨に穴を>
リハビリの第一歩として車椅子の操作を教わった。車椅子に一人で乗れるようになって何よりも嬉しかったのは自分でトイレに行けるようになったことだ。昼間は母が付き添ってくれた。夜は留次郎と知子それに父の3人が交代で付き添ってくれた。
しかし、短気者の父が同室の患者のいびきがうるさいと看護婦さんを叱りつけるので身の縮む思いであった。また、弟と妹が仕事があるので、そうそう付き添えない、と言って母と口論になった。誰の言い分ももっともなのですまないという気持ちにさせられた。
ここでもCTが撮られた。院長は中村さんに、沖縄でのCTフィルムを持ってきたかと尋ねた。中村さんは首を横に振った。
「どうして向こうの医者はフィルムば持たせんとか」
すこぶる院長の気分が悪い。出血直後のフィルムを見ないと正確な診断ができないらしい。馬場病院にきてから1週間後に沖縄から電話だと看護婦が伝えに病室にやってきた。車椅子をこいで受付の電話と取った。
「山下留蔵さんですか。沖縄の病院で付き添いをしていた良枝ですが。無事に帰られたかどうか気になって・・・」
「ああ、良枝さん。はい、元気です。ええ、うんうん、リハビリ、頑張ります」
受付には人目があった。もっと他に話ようもあったろうに。相撲取りのインタビューみたいな受け答えになってしまった。院長は久留米大学医学部の脳外科の講師である。筑後地方では手連の脳外科医として知られている。
脳外科医としては優秀らしいが口が悪い。機嫌に触ると誰かれなく怒鳴りつけると風評だ。それでも病院は繁盛している。院長回診で、脳の中に溜まっている血種を取り除かないと、おそらく手足は動かないだろうと言われた。
「硬かもんねえ。ほら、麻痺の強かけん、足が突っ張って膝が曲がらんもん、リハビリではこの硬かとは取れんじゃろうねえ」
「先生、手術はできますか!危なくはないですか?」
訪ねると、
「手術はできんことはなか。コンピュータで出血の場所ば正確に割り出して、頭蓋骨にドリルで穴ばあけて、細い管ば差し込んで血の塊ば吸い出す。やり損ないはでけん、一発勝負たい。手術ばするなら発症から40日以内にせんといかん。どげんするか。よーと考えとかんね」
と言いおいて病室を後にした。」
<家族会議> 
院長は簡単に言うが決断がつきかねた。父は家族で話し合うと言った。
「先生ば信用して手術ばしてもらうしかなかろうもん。このまま手足ん動かんならどうしようもあるめえが」
留次郎も父と同じ意見である。母と妹は、
「父ちゃんと留次郎がそげん言うならうちも母ちゃんも異論ななかけん」
仕事中の事なので労災の申請をしてほしいと家族は願った。だが院長も会社も労災は認められないだろうと言い放った。面倒なことには関わりたくないという態度が見え隠れした。留次郎は一人で会社側と交渉に当ってくれた。労災の申請はやるだけはやってみる。却下されたらD建設は社会保険を作りこれで治療を行う。日向建設は中村工事部長が。こっちからは留次郎が交渉に当った。
二人に任せるしかなかった。まだそれどころではなかったのである。左足のツッパリが異様に強く、膝が全然曲がらないのだ。足首にも内反と尖足の重複した障害が見られる。左手は早々と廃用手の宣告を受けてしまった。
手術をするかしないかで夜も眠れないほど悩んで枕を濡らした。医者の手元が狂って正常な脳細胞に損傷を与えたら。今よりもっとひどい状態になったらどうしようとか。そんなことを考えると恐ろしくて手術を受ける勇気がでないのである。35歳にもなって泣いている息子を捕まえて父は、
「おまや。クロボエよっとか。泣いたっちゃどげんもならんぞ、気合ば入れんか、気合ば」
あまりにも乱暴な父の言葉に嗚咽した。でも、このまま一生歩けないと家族への負担は大きい。特に母の心労はそうとうなものになるだろう。だからそれだけは避けたい。悩みに悩んで手術をすることにした。だが脳血管撮影の当日になって微熱が出たので撮影は中止され、以降オペの件は沙汰止みとなった。ある日、院長に手術はどうなりましたかと尋ねた。
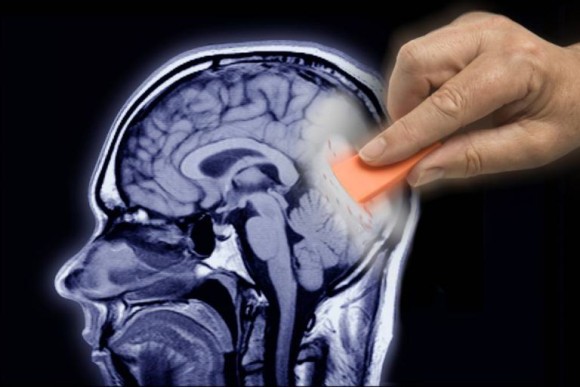
「手術ばしたけん、必ずよか結果が出るとは限らんもんねえ」
これを聞いて、リハビリにかけようと決心した。最悪の場合一生車椅子も覚悟した。そしてたとえ血の小便を流そうともリハビリに耐え、必ず歩けるようになろうと自分に誓ったのである。
外科的な処置で脳の中の血種を取り除かなかったらどうなるのだろう。
「脳の中の血種は自然に分解され血管の中へ取り込まれます。そして尿となって体外へ排出されます。敗れた血管は血小板が修復し、以前よりも強固となります」。
婦長がわかりやすく説明してくれた。
母は急に老け込んで腰が曲がり白髪も目立ち始めている。そんな母に車椅子を押してもらのはとても辛い。しかし、頼めるのは母しかいない。
「母ちゃん、もう一遍助けてくれんの、一人で歩かるるごつなるまで」
手術を見送ったことをPTの梅崎先生に話した。先生から本格的なリハビリ病棟のある国立療養所C病院への転院を打診された。これからリハビリは長期に及ぶ。家族が付き添うのにも限度がある。その点C病院なら完全看護だから安心というわけだ。
 
|