典子は手紙や電話を拒まなかった。友人に相談したらやめておいた方が良いと諭されたという。恋愛が止められないのなら駆け落ちするぐらいの覚悟が必要よ。そんな風なアドバイスをする者もいたという。彼女自身も戸惑い、途中から何度も引き返そうとした。しかし、一度燃え上がった恋の炎を消すことはできなかった。恋愛はその障壁が高ければ高いほど、当人たちは反対に燃え上がってしまう「恋の反作用」がある。周囲が反対をすれば火に油を注ぐ結果となる。

ふたりの気持ちは恋の臨界点に達しようとしていた。心の奥に潜んでいる男女の情念がくすぶりから火柱を上げようとしている。完全にふたりの世界ができあがっている。入所者と職員の交際は禁止されている。そんなことは承知の上なのだ。いきつくところまでいかないと収まらないだろう。休みの日には街外れの喫茶店で落ち合っていた。3キロも離れているのだが歩くのが辛いとは思わなかった。普段ならとうてい歩けない距離だが、典子と逢うためなら。という気持ちが麻痺した体を奮い立たせる。他の入所者や職員にバレやしないかと不安だったが、そういう緊張感が気持ちの高ぶりを加速させた。
退所を間近に控えた日曜日。典子の軽自動車で、景勝の海岸へ初めての長距離ドライブにでかけた。彼女は待ち合わせの場所に、サンドイッチを入れたバスケット持参で現れた。

「待った?」
「いや」
ほんとうは30分も早く着いて寒空の下で、麻痺足を氷のように冷たくしていたがおくびにも出さなかった。
「どこ行こうか」
「波戸岬に行こうか」
70キロ近い距離である。そんな遠いところへ入所者と職員がプライベートで出かけるなんて。典子の上司が知ったなら卒倒するかもしれない。
国道3号線を南下し博多で201号線に乗り入れた。混雑する福岡市内を抜け、前原、唐津、呼子と海岸沿いに典子は車を走らせた。思ったよりも早い時間に波戸岬に着いた。時計を見ると11時15分だった。
  
人気の無い松林に車を止め、サンドイッチを食べ始めた。熱いコーヒーもポットに用意されている。最初に私が飲み、同じ容器で典子はなんのためらいもなく口に運んで喉に流した、。黙って三角波の立つ海を眺めていた。大陸からの季節風が吹き荒れているが外に出てみた。思った以上に砂浜は歩きにくい。典子の肩につかまって少し歩いたが、足首の内反がひどくなって歩けない。ゆっくりと引き返し車の座席に腰を下ろした。彼女が運転席に着くと同時に体を右手で抱き寄せ唇を重ねた・・・。
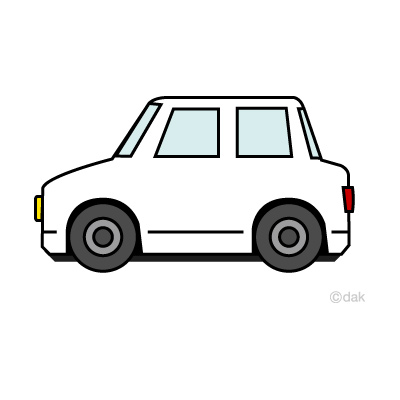 
1年半の訓練期間が終わった。1987年3月31日、リハビリセンターを退所した。この日は福岡の天神地下街で典子と待ち合わせをした。彼女の車で実家まで送ってもらうためだ。2時間かかって故郷へ着いた。私は、典子を家族に紹介した。
「初めまして。中島典子です」
「母です」
みんな驚くだろうと期待していたが反応は冷ややかだった。それもそのはずである。夕食が済むと母が大変なことを口にした。
「、母ちゃんなガンたい」
「えー、そりゃあ、ほんなこつね!」
「ほんなこつばい。町の健康診断でわかったと」
吃驚した。母がガンだなんて。そんな・・・。
「兄ちゃん、ほんなこつばい。4月18日、久留米医大で手術ばするごとなっとる」
弟がそう言った。
「心配するこつあいいらんけん。お医者さんもようなるち。言うとらっしゃるけん」
父の力強い言葉で少し安心した。
僕は、動揺していた気を取り直すと、、倉庫の裏の空き地で鶏を飼いたいと切り出した。
これはセンターにいるときから考えていたことである。週刊誌で鶏の放し飼いをしている人の記事が紹介されていたのである。それを読んでやってみたいなあと漠然と思っていた。
「そげなこつは止めとけ。匂いがして臭かけん。近所から苦情が出るぞ」
父は何でも反対した。昔からそうなのだ。車の免許を取るときも。自動車を買うときも。なんでも反対である。ま。これはどこの親もそうであるらしい。親の言うことを聞け。田舎ではこの一点張りである。
「最初は少しから始めるけん、よかろうもん」
すると、
「父ちゃん、兄ちゃんもあげん言いよるし、リハビリち思うとけばよかやんね」
父はそれから何も言わなくなった。
 
|